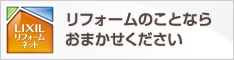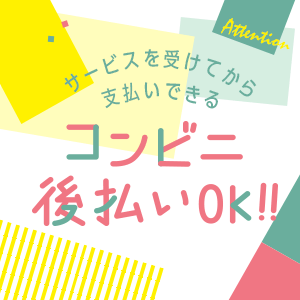水のコラム
災害時に使える仮設トイレ!マンホールトイレはどんなトイレ?【水道職人:公式】

仮設トイレの一つに、「マンホールトイレ」と呼ばれるトイレがあります。
マンホールトイレは災害時に使え、災害時のトイレ問題を解決に導けるという期待を持たれています。
しかし、マンホールトイレがどのようなトイレなのかをご存じない方が、多くいらっしゃるのではないでしょうか?
今回は、マンホールトイレの詳細や、マンホールトイレが抱える課題、徳島県の災害時のトイレ対策についてご紹介します。
マンホールトイレとは?

「マンホールトイレ」とは、下水道管路の上にある、マンホールを活用したトイレです。
災害時にマンホールの上に簡易便座やパネル、テントなどを設けることで、マンホールはトイレに姿を変えます。
マンホールトイレは衛生的
地震などの災害では水道が使えなくなることが多く、トイレが流せない問題が発生します。
災害現場は瓦礫(がれき)などで溢れ、平時に比べて衛生面が損なわれた状態です。
その中で排泄物も流せずにたまっていくと、環境はさらに悪化し、感染症が蔓延(まんえん)する危険があります。
そして悪臭にも苦しめられるのです。
このような状況を打開するために、マンホールトイレは活躍します。
マンホールトイレの下は下水道です。
マンホールトイレの上で排泄すると、排泄物はマンホールの中に落ち、下流の下水道管に流れていきます。
その結果、地上では衛生面を保てるのです。
また、一部のマンホールトイレには水洗用水投入口も設置されます。
万が一マンホールの中で排泄物が停滞した場合にも、水洗用水投入口から水を流し入れることで、排泄物を下流の下水道に押し流せます。
マンホールトイレは設置が簡単
マンホールトイレの設置は非常に簡単です。
公園や道路などにあるマンホールトイレのふたを開け、その上に専用の便座、パネル、テントを設置すれば完成です。
マンホールトイレに使えるマンホールのふたは、「マンホールふた開閉バール」で開けられます。
マンホールトイレに使えるマンホールがある場所では、マンホールふた開閉バールを保管しているため、万が一に備えて保管場所を確認しておきましょう。
マンホールトイレの設置にはガイドラインがある
マンホールトイレは、既にあるマンホールを活用しているから、全てのマンホールをトイレとして使えるという認識を持っている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、その認識は間違いです。
マンホールトイレには国や自治体が定めたガイドラインがあり、ガイドラインに則って、一部のマンホールをマンホールトイレとして活用しているのです。
通常のマンホールではなく、マンホールトイレとして使えるマンホールの場合、ふたに「防災用トイレ」などの記載があります。
ガイドラインでは防犯上の安全面や、マンホールトイレを使う上での快適性、衛生面を保つための対策などが定められているのです。
マンホールトイレの形式は複数
マンホールトイレで排泄された排泄物の処理方法は、マンホールトイレの形式によって異なります。
マンホールトイレの形式は、大きく分けて3つあるでしょう。
- 本管直結型
- 流下型
- 貯留型
3つの形式には、それぞれにメリットがあります。
本管直結型
マンホールの上に、マンホールトイレの便器などを設置するだけで利用できるでしょう。
排泄物は、下水道管路からマンホールトイレ用の配管が引かれており、上流から流れてくる下水の力で下流まで流れます。
トイレのために水源を準備する必要がなく、現在設置のあるマンホールをそのまま活用できるメリットを持つ形式です。
流下型
下水道管路に、下水道管に接続する形で排水管を新たに設置します。
この排水管の上にマンホールがあり、マンホールトイレの便器などを設置して使います。
流下型では水源が別途必要になるため、水洗用水投入口も設置が必要です。
貯留型と比較すると、排水管の管径が小さめで良いというメリットを持つ形式です。
貯留型
流下型のように、下水道管路に排水管を設置した上で、マンホール内や汚水マスの中に貯留弁も設置し、排水管を貯留槽として活用します。
また、貯留槽を別途設置するケースもあります。
流下型と同様に、水源が必要です。
マンホールトイレにもキャパは存在します。
下水道管路や下水道管の状態によっては、マンホールトイレを使えなくなることもあるでしょう。
しかし、貯留型は貯留弁や貯留槽という、排泄物を留め置く機能を持っています。
貯留型は、下水道管路などの状態を問わずに、一定期間使えるというメリットを持つ形式です。
参考:マンホールトイレの整備・運用チェックリスト┃国土交通省
マンホールトイレの課題

マンホールトイレの設置や維持管理には、多くの課題があります。
まだまだ導入が進まない理由は、抱えている課題を解決するには時間を要するためでしょう。
残留物
マンホールトイレでは、トイレを使った後に、便器の中に排泄物やペーパーの残留物が残るという問題があります。
排泄物が便器の中に残れば、悪臭の原因になりますし、排泄物が付着しやすい状態になってしまいます。
こうなると、衛生的とは言い難く、トイレ問題は解決しないと同義です。
便器の中に残留物を残さないためには、水で流すことが有効ですが、水道が止まっている環境でトイレに使える水はないでしょう。
トイレに使える水があれば、マンホールトイレを使うという必要性もありません。
残留物を残さないための課題解決が必要です。
衛生面
マンホールトイレでは、便座を清潔に保つ方法も求められます。
マンホールトイレでは、便座に排泄物が飛び散っていることや、便座が汚泥などで汚れていることがあります。
平時であれば掃除できれいにできますが、災害時に掃除道具が潤沢に準備されていることは少ないでしょう。
仮に掃除道具が揃っていたとしても、洗剤を流す水や、排泄物などが付着したごみを処理できる環境はありません。
アルコール除菌するという方法もありますが、そのためにはアルコール除菌するためのアルコールを潤沢に準備しなければなりません。
災害時は水道が使えず、手指の除菌でも必要となるものを、トイレに大量に消費できるかというと、それは難しいかもしれません。
また、掃除道具にしろアルコールにしろ、準備するためには費用が必要で、それらを長期保管したり、起源が切れたものを交換したりする管理も必要です。
照明設備
マンホールトイレは屋外のマンホールを活用するため、夜間は照明設備がないためにトイレを使えないという問題があります。
また、トイレに向かう道中にも照明設備がなく、災害時の崩れた道を明かりがない状態で進むのは大変危険です。
そして、照明がない暗闇の中では犯罪も起こりやすい傾向があります。
マンホールトイレの導入には、夜間の安全面の対策も求められるのです。
参考:マンホールトイレの実用課題と対策検討~大規模断水によるマンホールトイレの実用例~┃国土交通省
【徳島県の対策】避難所のトイレ問題を解決するためのマニュアル

災害時のトイレ問題は、避難所生活を送る上で大きなストレスを与えるものです。
自宅避難であればまだ堪えられる問題も、避難所のように多くの人が避難している場所では堪えがたいこともあります。
そのような苦痛を軽減するために、徳島県では避難所で快適にトイレを使うためのマニュアルを準備しているのです。
マニュアルでは、災害が起きた直後のトイレ対策の初動や、携帯トイレの設置、簡易トイレの設置について記載があります。
また、凝固剤の使い方についても写真つきで説明があるため、有事の際に混乱して使い方が分からなくなったときも活用できるでしょう。
それだけではなく、使用済みのトイレの保管法や処理方法、水源の確保についても詳しく記載されています。
万が一に備え、一度目を通してみてください。
参考:「徳島県避難所快適トイレ・実践マニュアル」の策定について┃安心とくしま
災害に備えて自宅でもトイレを準備しておこう

日本は地震大国です。
いつなんどき、大きな地震が起こってもおかしくはない、そんな国で私たちは生活しています。
令和に入ってから大きな地震のニュースは多く、徳島県でも大きな地震が起こる可能性があります。
何事もなく平和に過ごせることが一番ですが、万が一の際に備えて、ご自宅でも災害用トイレを準備しておきましょう。
既に準備をしている方も多くいらっしゃるとは思います。
準備が済んでいる方は、使用期限がまだ過ぎていないかを定期的に点検しましょう。
また、家族の人数が増えて準備している災害用トイレでは数が足りないという事態にならないように、ライフステージの変化に合わせて点検することもおすすめです。
災害時のトイレストレスは大きなもので、トイレを使えないという理由でトイレを我慢したり、飲食を控えたりして、健康を害する可能性もあります。
トイレ問題を解決する準備を講じておくことで、災害時のストレスが一つ軽減されるでしょう。