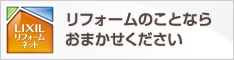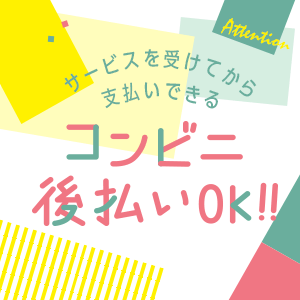水のコラム
【トイレの水が流れない】原因と対処法|落ち着いて解決するために

トイレの水が流れないトラブルは、日常生活において最も困る出来事の一つです。原因は様々ですが、慌てずに対処することで多くの場合は解決できます。
このページでは、トイレの水が流れなくなった際の主な原因と対処法、そして予防策までを詳しく解説します。まずは落ち着いて状況を確認し、適切な対応を取りましょう。
トイレの水が流れないときは慌てずに確認を

トイレの水が流れないトラブルは、大きく分けて「タンクに水が溜まらない」「タンクの水が便器に流れない」「便器の排水口につまりがある」の3つのケースがあります。
まずは、どのケースに当てはまるかを確認することで、効果的な対処法を見つけることができます。
トイレトラブルの種類と対処の基本
トイレトラブルが発生したら、まず以下の3点を確認しましょう。
- タンクに水は溜まっているか
- レバーを回したときの手応えはあるか
- 便器内に異常な水位上昇はないか
この確認により、トラブルの種類を特定でき、適切な対処法を選択できます。
トイレタンクから水が流れる基本的な仕組み
トイレタンクには、水量を調整する「浮き玉(フロート)」と「ボールタップ」、水を便器に流す「フロートバルブ」という重要な部品があります。
レバーを回すと、チェーンを介してフロートバルブが持ち上がり、タンク内の水が便器に流れ込みます。この時、浮き玉が下がることでボールタップが作動し、新しい水が補給されるという仕組みです。
また、タンク内には水位が上がりすぎるのを防ぐ「オーバーフロー管」も設置されており、これらの部品が正常に機能することで、トイレは適切に動作します。
トイレの水が流れない主な原因

トイレの水が流れないトラブルは、発生箇所によって大きく3つのケースに分類できます。それぞれの原因を理解することで、適切な対処法を選択できます。
修理の前に、まずはどのケースに該当するか確認してみましょう。
タンクに水が溜まらないケース
タンクに水が溜まらない主な原因として、以下のようなケースが考えられます。
止水栓の問題
止水栓が完全に閉まっているか、またはつまりが発生している可能性があります。引っ越し直後や水道工事後によく起こるトラブルです。
給水装置の不具合
タンク内の浮き玉(フロート)やボールタップといった給水を制御する部品に問題が生じている場合があります。特に経年劣化による故障が多く見られます。
フィルターの目詰まり
給水管に取り付けられたフィルターが、長年の使用で目詰まりを起こしているケースです。水の流れが悪くなり、タンクへの給水が不十分になります。
タンクに水はあるが便器に流れないケース
タンクには水が溜まっているのに便器に水が流れない場合は、以下の原因が考えられます。
レバーの故障
トイレレバーの破損や軸の折れにより、レバーを回しても水が流れなくなることがあります。レバーが空回りする感覚があれば、この可能性が高いです。
フロートバルブの劣化
タンク底部にあるフロートバルブが劣化すると、水が正常に流れなくなります。ゴム部分の亀裂や変形が主な原因です。
チェーンの不具合
レバーとフロートバルブをつなぐチェーンが外れたり、長さが合っていなかったりすると、水が流れなくなることがあります。
便器の排水口につまりがあるケース
便器の排水口につまりがある場合、以下のような原因が考えられます。
トイレットペーパーの詰まり
一度に大量のトイレットペーパーを流すと、十分に溶けきらずにつまることがあります。節水型トイレではより起こりやすい傾向にあります。
異物の混入
誤ってボールペンやアクセサリーなどを落としてしまい、それが原因でつまるケースがあります。子どものいる家庭では特に注意が必要です。
尿石の蓄積
長期間の使用で尿石が徐々に蓄積され、排水管が狭くなることがあります。定期的な清掃で防ぐことができます。
自分でできる応急処置と対処法

トイレの水が流れない場合、軽度のトラブルであれば自分で対処できるケースも多くあります。ただし、これらの対処は、固形物による詰まりや重度の故障には適していません。
状況を正しく判断し、無理のない範囲で対処することが重要です。家庭でも実践できる応急処置や解決方法を詳しくご紹介します。
バケツを使った応急処置の方法
バケツを使った水流しは、最も一般的な応急処置です。適切な手順で行うことで、多くの場合で効果を発揮します。
用意するもの
- ●バケツ(5-6L程度の水が入るもの)
- ●新聞紙やタオル(床の養生用)
- ●ゴム手袋
- ●雑巾(水がはねた時の拭き取り用)
作業の手順
- 床に新聞紙やタオルを敷いて養生します
- バケツに水を5-6L程度入れます(水量が多すぎると水はねの原因になります)
- 便器内の水位が高い場合は、柄杓などで水を減らしておきます
- バケツの水を腰の高さから勢いよく流し込みます
- 水を流したら、すぐに便器内の様子を確認します
作業の注意点
- ●一度で解消しない場合は2-3回繰り返します
- ●水位が上がってきたら、すぐに作業を中止してください
- ●最後に必ず封水を作るため、3-4Lの水を静かに流し入れます
お湯を使ったつまり解消法
お湯を使用する方法は、特にトイレットペーパーが原因のつまりに効果的です。温度管理が重要なポイントです。
用意するもの
- ●40~50℃のお湯(4-5L程度)
- ●バケツまたは柄杓
- ●ゴム手袋
- ●温度計
作業の手順
- 便器内の水位を下げておきます(高すぎると溢れる危険があります)
- 40~50℃のお湯を便器に静かに注ぎます
- 1時間程度置きます(この間にトイレットペーパーが溶けやすくなります)
- 時間が経過したら、水を流して確認します
- 効果が不十分な場合は、もう一度繰り返します
作業の注意点
- ●熱湯(60℃以上)は絶対に使用しないでください
- ●お湯を入れる際は、やけどに注意してください
- ●陶器が熱で割れる可能性があるため、急激な温度変化は避けます
クエン酸と重曹による対処法
クエン酸と重曹を組み合わせた方法は、軽度のつまりに効果的です。発泡作用でつまりを緩めることができます。
用意するもの
- ●クエン酸(200cc)
- ●重曹(100cc)
- ●50℃程度のお湯(2-3L)
- ●計量カップ
- ●ゴム手袋
作業の手順
- 排水口に重曹を振りかけます(粉が均一に広がるように注意)
- その上からクエン酸をまんべんなく加えます
- 発泡したら50℃程度のお湯をゆっくり注ぎます
- 1時間ほど放置します(この間に発泡作用で汚れが浮き上がります)
- 最後に水を流して確認します
作業の注意点
- ●発泡時に目に入らないようゆっくり作業する
- ●適切な分量を守ること
- ●お湯の温度管理に注意
タンク内の部品調整による解決方法
タンク内の部品調整は、適切な工具と手順で行うことで、多くの問題を解決できます。
用意するもの
- ●マイナスドライバー
- ●ウエス
- ●軍手
- ●懐中電灯
止水栓調整の手順
- 止水栓を一度時計回りに回して完全に閉めます
- タンクの水を流し切ります
- 止水栓を反時計回りにゆっくり開けていきます
- オーバーフロー管の「WL」マークまで水が溜まるよう調整します
- レバーを操作して水の流れを確認します
浮き玉調整の手順
- タンクのふたを丁寧に取り外します
- 浮き玉の位置と動きを確認します
- アームが引っかかっている場合は、慎重に直します
- 水位を見ながら浮き玉の位置を調整します
- 適切な水位になるようアームの角度を変えます
作業の注意点
- ●部品を無理に動かさない
- ●調整後は必ず動作確認をする
- ●異常を感じたら作業を中止する
これらの方法で解決できない場合や、作業中に異常を感じた場合は、すぐに作業を中止し、専門業者へご相談ください。無理な修理は、かえって症状を悪化させる可能性があります。
トイレトラブルを防ぐための予防策

トイレのトラブルは、適切な使用方法と定期的なメンテナンスで予防できます。快適なトイレ環境を維持するための具体的な対策をご紹介します。
日常的なメンテナンスのポイント
日々の簡単な手入れが、トラブル予防の第一歩です。継続的なケアで清潔で快適なトイレを維持しましょう。
毎日のケア
- ●便器のフチ裏や便座の拭き掃除
- ●床の水気や汚れを乾いた布でふき取る
- ●便器の水を流して、流れ具合を確認
- ●異常音や水漏れの有無をチェック
週1回のケア
- ●トイレブラシで便器内をしっかり洗浄
- ●トイレ用洗剤で水アカや尿石を除去
- ●タンクのフタを開けて内部を確認
- ●便座やレバー周りの念入りな清掃
月1回の重点ケア
- ●排水口まわりの汚れを専用ブラシで除去
- ●タンク内の部品(浮き玉、フロートバルブなど)の動作確認
- ●止水栓を数回開け閉めして動作確認
- ●便器と床の接合部の水漏れチェック
トイレ使用時の注意点
正しい使用方法を心がけることで、多くのトラブルを未然に防げます。家族全員で以下のポイントを共有しましょう。
絶対に流してはいけないもの
- ●ウェットティッシュ(水に溶けにくくつまりの原因に)
- ●生理用品(吸水して膨らみ、つまりの主な原因となる)
- ●ティッシュペーパー(水に溶けにくく管内に付着)
- ●髪の毛(排水管に絡まり、深刻なつまりを引き起こす)
- ●異物(おもちゃ、アクセサリーなど)
正しい使用方法
- ●トイレットペーパーは2-3回に分けて流す
- ●レバーは最後まで確実に押し下げ、途中で戻さない
- ●便器に強い衝撃を与えない(ひびが入る可能性あり)
- ●市販のつまり防止剤は説明書通りに使用
節水に関する注意点
- ●タンクに節水のためのペットボトルは入れない
- ●節水型トイレの場合は専用のトイレットペーパーを使用
- ●水流が弱くなってきたら要注意
定期的な点検で防ぐトラブル
3ヶ月に1回を目安に、以下の点検を行いましょう。早期発見が修理費用の節約につながります。
タンク内部の点検ポイント
- ●浮き玉の動きがスムーズか
- ●フロートバルブにヒビや劣化がないか
- ●チェーンの張り具合は適切か
- ●水が適切な水位まで溜まるか
便器まわりの点検箇所
- ●便器と床の接合部に隙間や水漏れはないか
- ●便器に傷やヒビが入っていないか
- ●排水時に異音はしないか
- ●水の流れは均一か
配管まわりのチェック
- ●止水栓はスムーズに回るか
- ●給水管から水漏れはないか
- ●排水管から異臭はしないか
- ●床下や天井に水漏れの形跡はないか
徳島県内のホームセンターでトイレ用品を購入
トイレ用品の購入は、お近くのホームセンターが便利です。
コーナン徳島藍住店
住所:徳島県板野郡藍住町住吉千鳥ケ浜87番地2
営業時間:7:00〜21:00
県内最大級の品揃えで、トイレ関連商品も充実。DIY初心者でも安心の親切な説明付き。
DCM万代店
住所:徳島県徳島市万代町6丁目3番地
営業時間:9:30〜20:00
特徴:トイレ用品の専門コーナーあり。スタッフの商品知識が豊富で相談しやすい。
ホームプラザナフコ鳴門店
住所:徳島県鳴門市里浦町粟津西開168-1
営業時間:8:00〜20:00
トイレ掃除用品から修理部品まで幅広く取り扱い。ポイントカードでお得に購入可能。
トイレつまり発生時の注意点

トイレがつまった時、焦って誤った対処をしてしまうと、かえって状況を悪化させる可能性があります。避けるべき対処法と、専門業者に依頼すべき状況について解説します。
してはいけない危険な対処法
誤った対処は、トイレの破損や水漏れなど、より深刻な問題を引き起こす可能性があります。以下の方法は絶対に避けてください。
絶対に避けたい対処法
- ●熱湯を直接流す(便器の破損や排水管の劣化の原因に)
- ●市販の強酸性洗剤の使用(排水管を傷める可能性大)
- ●無理な道具の使用(便器を傷つける恐れあり)
- ●便器に強い圧力をかける(陶器が割れる危険性)
危険な市販品の使用
- ●強力な薬品系パイプクリーナー
- ●金属製の配管用ワイヤー
- ●工業用の強酸・強アルカリ洗剤
- ●排水管用の高圧洗浄機
業者に依頼すべき状況の見極め方
以下のような状況が発生した場合は、すぐに専門業者への依頼をお勧めします。
すぐに業者を呼ぶべき症状
- ●水位が下がらず、溢れそうな状態が続く
- ●異物を誤って流してしまった
- ●排水時に異常な音がする
- ●床や壁に水漏れの跡がある
自力での改善が難しい状況
- ●複数回の応急処置を試しても改善しない
- ●頻繁につまりが発生する
- ●便器と床の接合部から水が漏れている
- ●排水管からの異臭が止まらない
トイレのトラブルは、早めの専門家への相談が、結果的に修理費用の節約につながります。無理な対処は避け、状況に応じて適切な判断をしましょう。
トイレの水が流れないときは「とくしま水道職人」へ
トイレのトラブルは、ご自身での対処が難しい場合や状況が悪化した場合、すぐに専門家への相談をお勧めします。とくしま水道職人では、24時間365日受付体制でトイレのトラブルに対応しています。
緊急のトイレトラブルには、受付後最短30分で現場に到着し、経験豊富な技術者がトラブルの原因を的確に診断した後最適な修理方法をご提案します。作業前には修理内容と費用を詳しくご説明し、お客様にご納得いただいてから作業を開始しますのでご安心ください。
料金体系も明確で、夜間休日の追加料金はありません。お支払いは現金の他、クレジットカードやQRコード決済など各種対応可能です。修理後は動作確認を徹底し、作業内容の説明と再発防止のアドバイスもさせていただきます。
トイレのトラブルでお困りの際は、お気軽にご相談ください。